
ここのところシリーズ化している
「自宅飲食店開業のQ&A」
を今回も回答していきたいと思います。
※過去のものはこちらから↓
自宅飲食店開業のQ&A
【疑問1】自宅が賃貸だけど飲食店を開ける?
原則として賃貸契約に「営業利用不可」とある場合は開業できません。
大家さんに確認し、了承が得られれば可能性はありますが、飲食業はクレーム対象になりやすい業種なので、かなり難しいように個人的には感じます。
チェックするべき項目は以下の通りです。
- 賃貸契約の内容を確認:「住居専用」「営業利用禁止」と記載があれば、そのままでは営業不可。
- オーナー・管理会社に必ず相談:「静かな個人営業」「予約制」「週2営業」など営業スタイルを丁寧に伝えれば、了承が得られるケースも。
- 近隣住民への説明と配慮も必須:もし開業OKでも、「営業前に挨拶まわり+案内チラシを持参する」など、ご近所への信頼づくりが重要です。
【疑問2】開業届ってどこに出すの?
開業前に「個人事業の開業・廃業等届出書」を最寄りの税務署に提出します。
- 提出先:開業する場所を管轄する税務署
- 提出方法:窓口持参/郵送/e-Tax(マイナンバーカードでオンライン可)
- 提出期限:開業日から1ヶ月以内が目安(遅れても罰則はないが、青色申告の控除が受けられなくなる可能性あり)
【疑問3】青色申告と白色申告、どっちがいいの?
青色も白色も結局やることはほぼ同じなので、最大65万円の控除がある「青色申告」がおすすめです。
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除
- 赤字の繰越が最大3年可能
- 家族に給与を支払える(専従者控除)
デメリット
- 帳簿の記帳が必要(ただし会計アプリで初心者でも簡単に)
白色申告の特徴
- 書類は簡単だが、控除や優遇はほぼなし
【疑問4】SNSは開業前から始めたほうがいい?
絶対やった方がいいです!
開業前の準備風景、試作、インテリアなどを発信して「オープン待ちのファン」を作れます。
個人的におすすめしたいのは、より情報が伝わるYouTubeの横長動画ですね。
動画は写真よりも伝わる情報量が多いので、より「行ってみたい!」という心理状況を作れます。
投稿例
- メニュー開発の様子(失敗も◎)
- お店作りの裏話
- インテリア・食器選び
- 自己紹介・ストーリー
メリット
- 応援してくれるファンがつく
- オープン後の初動集客がスムーズ
- 投稿が「信頼の証明」になる
【疑問5】飲食店の名前ってどう決めればいい?
名前はコンセプト・記憶性・検索性の3つを意識。
- 覚えやすく、読みやすいもの
- 業種をイメージできる
- カナ読みで4文字以内が理想
- ありがちな名前にしない
- 難しい漢字や外国語を使用しない
- 読んだ時に濁音・半濁音が入っている
- 店名候補がネット上に存在しない
【疑問6】営業場所(自宅)の住所を公開するのが心配
「住所の公開」は、自宅飲食店のデメリットの一つでもあります。
自宅と言っているだけあって「店舗の住所=自宅の住所」となりますからね。。
ホームページなどには番地の一部だけを公開するという施策もありますが、正直「自宅の住所をさらしたくない」という人は、自宅飲食店での開業には向いていないかもしれません。
Googleマップなどの「インターネットからの集客」をしっかり行いたい人は、ある程度リスクを取りましょう。
【疑問7】飲食店保険って必要?
できれば入っておいた方が良いでしょう。
特に「火災保険」「生産物賠償責任保険(PL保険)」は重要度が高めです。
火を使う飲食店は「火災保険」には入っておきましょう。
「PL保険」は店舗で作ったものによってお客様に被害が生じた際の、損害を補償する保険です。
例えば食中毒が発生した場合などに、治療費、入院費や通院費、慰謝料や損害賠償などを補償してくれます。
小規模向けの格安プランも色々あります。
保険料は経費になりますが、年間の保険料の上限は決めておきましょう。
【疑問8】営業許可を取るまでどのくらい期間がかかる?
以下が一般的なスケジュールです。
- 【相談→申請→検査→許可】の流れ
- 申請から許可証発行まで7~14日が平均
- ただし、設備不備や図面不備があると1ヶ月以上かかるケースも
通常は申請から10日前後で許可がおりますが、設備の改善指導が入ると1ヶ月以上かかることもあります。
うちは2度の改善指導が入り、開業できたのは1ヶ月半後でした。
もし開業日が決まっていて、SNS等で宣伝していた場合は、余裕をもって2ヶ月前に保健所に申請をするのが良いと思います。
【疑問9】メニューの試作や価格設定はどう進めればいい?
メニューの試作
メニューの試作は、家族、友人、知人に試食してもらい、味と価格のフィードバックをもらうのが効果的だと思います。
特に家族には「本音」をしっかり言ってもらいましょう。
ここで曖昧な意見だと、曖昧なものをお客さんに提供することになるので、必ず本音で語ってもらい、開業までにブラッシュアップを重ねるようにしましょう。
価格設定
価格設定は、原価率30%前後を目安にしつつ、地域の飲食店の平均的な価格、競合店の価格なども参考に決めるとよいと思います。
また、店舗が成長してきてサービスや調理技術が上がってきたら、「成長分」を価格に反映させるのも良いと自分は考えています。
この考えがあれば、食材価格が上昇するような外的要因に関わらず「独自に値上げ」することが可能になります。
もし一人、または家族のみで経営する場合は、人件費がかからないので、その分を原価に充てて「コスパの良い価格」にすることも可能です。
うちも家族でやっているので、人件費がかからない分をお客さんへ還元しています。
【疑問10】開業準備におすすめのスケジュールは?
飲食店の開業本などでは、よく「1年前から準備を行いましょう」と書かれている場合が多いのですが、個人的には
「開業日の3年前、遅くとも2年前から準備を進める方が良い」
と考えています。
1年前から準備を行える人は、恐らく飲食業界での経験が長い人や、飲食業の経営・マーケティングなどのスキルがある人などに限られると思います。
自分もそうでしたが、飲食業のことを何も知らない素人が飲食店を開業しようと思ったら、勉強・経験・準備にそれなりの時間がかかるはずです。
自分が開業しようと考えたのが25歳の時で、実際に開業したのが35歳の時でした。
この10年の間に、経営の勉強、飲食業界での経験、開業資金の貯金(これはIT業でしたが)と、やることがとても多かったです。
まとめ
ということで今回も「自宅飲食店の開業前の悩み・疑問」をQ&A方式で回答しました。
今回特に大事だなと思ったのが、
「【疑問5】飲食店の名前ってどう決めればいい?」
ですね。
以前
「2020年以降の飲食店の「店名(屋号)の決め方」とは? 最重要は「ネット上にまだ無い店名」!なぜなら…」
という記事でも書いていますが、
店名を決める時はしっかり吟味した方が良いです。
うちが『カフェガパオ』という店名にしたのも、今回紹介したポイントを全てクリアしていたので採用しました。
- 覚えやすく、読みやすいもの→「ガパオ」が覚えやすい
- 業種をイメージできる→「ガパオ」はタイ料理でも使われるホーリーバジルのこと
- カナ読みで4文字以内が理想→「ガパオ」が3文字
- ありがちな名前にしない→タイ料理屋はタイ語が多い
- 難しい漢字や外国語を使用しない→カタカナのみ使用
- 読んだ時に濁音・半濁音が入っている→「ガパオ」には2語入っている
- 店名候補がネット上に存在しない→2012年の開業時には「カフェガパオ」という店名は存在していなかった
お客さんからもよく「ガパオさん」と呼ばれていて、3文字&濁音・半濁音があると記憶に残りやすいようです。
あと夏場になるとメディアで「ガパオライス」が紹介される時が多いのですが、こういう時に「近くのガパオライス」で検索した人が多く訪れることがあります。
この時、店名がガパオライスが紐付けされていることもあり、ネット検索で引っ掛かりやすくなっています。
インターネットを意識した店名付けは「ネット社会」の現在では、最も重要視するポイントかもしれないですね。
今回の記事が今後自宅飲食店を開業しようと思っている人のお役に立てば幸いです。
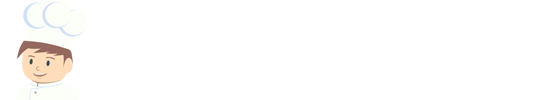


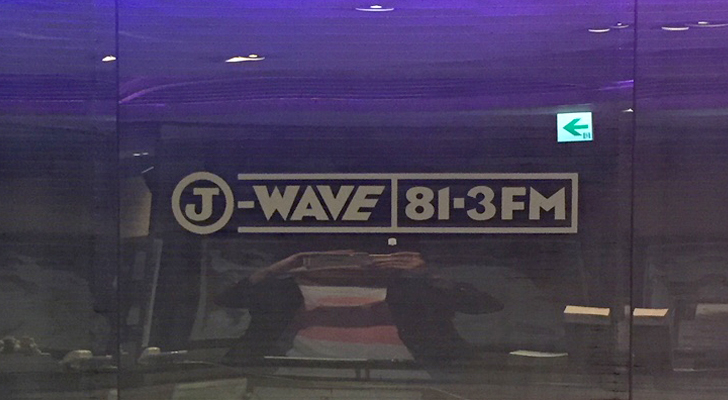
どうもヨッシー店長です。