
このブログではこれまで
「自宅飲食店は潰れにくいビジネスモデルです」
とお伝えしてきましたが、
飲食店開業素人の人が見落としてる
「致命的なミス」
があります。
今回はそんな致命的なミスの中から自宅飲食店の開業で
「やりがちなミス5選」
をお伝えしていきたいと思います。
ミス①:保健所の許可を“取れるつもり”で進める
1つ目のミスは、「保健所の許可を取れるつもりで進める」ということです。
『自宅飲食店』というと、
「自宅にキッチンがあるんだから、すぐに開業できるはず」
と考えてしまう人も多いですが、実際にはすぐに開業することはできません。
なぜなら飲食店営業をするには「営業許可」が必要で、この営業許可を満たすには
「営業用設備としての基準をクリアする必要」
があります。
具体的にいうと、
- 厨房と客席がドアで分かれている。(スイングドアなどでもOKな場合もある)
- 厨房のシンクは、二槽以上必要。
- 手洗いシンクが別途必要。(固定の消毒装置付きも必要)
- 床材が耐水性になっている。
- 冷蔵庫がある。(温度計が必要)
- 食器などをしまう棚に扉が付いている。
- 換気設備がある。
- トイレには手洗いシンクがある。
- 店舗と自宅の境目にドア等がある。
- 厨房内は耐水壁シートになっている。
などの基準があります。
うちの場合は、新築設計時に確認したはずでしたが…
- 手洗いシンクが小さい → 保健所指定の大きいものを別途購入
- 厨房内は耐水壁シートが無かった → 追加工事
- 厨房と客席の境目にのドアのサイズが小さかった → 追加工事
と、後から気付く箇所も結構ありました(^-^;)
とりあえず保健所の検査は2回目でOKが出ましたが、
「保健所のチェックは相当厳しかった」
というのが、個人的な印象です。
「営業許可を出す」ということは「保健所も責任を負う」ということでもあるので、チェックは基本的には厳しいと思っておいた方が良いですね。
ミス②:家族の同意を軽く見ている
2つ目のミスは、「家族の同意を軽く見ている」ということです。
自宅飲食店を家族(夫婦)で経営する場合はまだ良いのですが、一人(夫か妻どちらか)で経営を始める場合は、注意が必要です。
一人で経営する場合、ついつい
「自宅営業=自分一人の判断で何でもできる」
と思いがちです。
でも実際には、匂い・音・来客・時間帯・清掃・トイレの使用など、家族にも影響が出る部分が多数あります。
最初は家族が「なんとなくOK」と言ってても、経営が始まってから不満爆発…というケースも多いです。

そうならないためにも、開業前に生活動線や役割分担などを話し合っておくことが必要、かつ重要です。
もし夫婦であれば「ここまでは妥協する」という部分を明確にしておくことが大事でしょう。

開業から数年後には、妻にも「飲食業は家業である」と理解してもらえ、土日祝の忙しい日は終日営業に入ってもらえるようになりました。
(妻に感謝m(_ _)m)
ミス③:「売れるメニュー」より「作りたいメニュー」を優先する
3つ目のミスは、「売れるメニューより作りたいメニューを優先する」ということです。
これは本当によくある話で、「自分の好きな料理」や「こだわりの逸品」にこだわるあまり、
- 仕込みが多すぎる
- 原価が高すぎる
- 利益率が低い
- お客さんが求めていない
など、
「ビジネスとして成立しないメニュー構成」
になることがあります。
特に「頑固な職人気質」の人によく見られる傾向で、商圏ニーズ(お客さんが求めるもの)とミスマッチがあると、なかなか常連客が定着せず、集客に苦労することもあります。
そうならないためにも、自宅飲食店を開業する場合は
「職人」になるのではなく、「経営者」になる
ことを意識しないといけません。
開業前に市場リサーチすることはもちろんですが、開業後も「売れる×自分らしい」を探りつつ、その地域でお客さんが求めているものに「柔軟に変化していく」ことが大事になってきます。

ちなみに以前の料理提供時間は長い時で1時間かかっていましたが、現在は長くても30分以内には料理が出るようになりました。
ミス④:集客を「インスタでなんとかなる」と思っている
飲食業に限らず、ビジネス全般で商品を販売するまでのプロセスで、もっとも大事なことがあります。
それは「集客」です。
集客ができないと、世界一良い商品であっても、売れることはありません。
逆にいうと、集客がしっかりできてさえいれば、商品は自ずと売れます。
自分はかれこれ23年程飲食業に携わっていますが、「集客をないがしろ」にしている飲食店は多いように感じます。
特に飲食業界未経験で1年以内に廃業してしまう店は、それに当てはまってしまっているような気がします。
よくあるのが、
『集客は大事だって聞くけど、まあインスタやっておけば大丈夫でしょ』
という浅はかな考えです。
確かにインスタグラムは飲食店との相性は良いですが、集客効果が出るまでには時間がかかります。
また、投稿内容も『是非行ってみたい!』と思わせる内容を連発させないと、集客にまでは繋がらない可能性があります。
長期で継続し、「アカウントを育てていく」ことが重要になってきます。
飲食店の集客方法は、主に
- アナログ手法:看板、チラシ、地域情報誌、地域施設の情報掲載、知人友人のクチコミ、など。
- デジタル手法:Googleビジネスプロフィール、インスタグラム、LINE公式アカウント、など。
があります。
2020年以降はデジタル手法が主流になってきましたが、それでもまだまだアナログ手法も集客効果があります。
開業時にまずは広く浅くやってみて、その店舗に合う手法を見つけて、徐々に絞っていきましょう(^-^*)

- ホームページ
- Googleビジネスプロフィール
- LINE公式アカウント
- インスタグラム
- 看板
ですね。
ちなみに、ホームページは最終的に「知人友人のクチコミ」に繋がるような設計にしています。
集客に関しては、過去の記事でもよく書いていますので、こちらからご覧ください。
ミス⑤:売上=利益だと思っている
自宅飲食店を開業する人の中には、「自宅で気軽に飲食店を開業してみよう」と思って、経営や経理の知識が無いまま開業してしまう人も少なくありません。
知識不足の為、「売上=利益」だと思っている人もたまにいます。
売上(うりあげ)
お客さんからもらった お金の総額。
例えば、ラーメン1杯800円を100杯売ったら、
売上=800円 × 100杯 = 80,000円
利益(りえき)
売上から「かかったお金(コスト)」を引いた儲け(もうけ)のこと。
例えば、ラーメン1杯を作るのに
材料費 300円
光熱費・人件費・家賃などを1杯あたりに換算して 200円
だったら、1杯の原価は 500円。
この場合、利益は
利益=売上(800円)- 原価(500円)= 300円
それが100杯分なら
300円 × 100杯 = 30,000円(これが利益)
材料費や光熱費以外にも、広告費、決済手数料、掃除道具や消耗品などの備品代、テイクアウトもやっていればその容器代など、他にもかかる費用が結構あります。
それ故、「1日中仕込み+営業しても利益は1万円しか残らない」なんてケースもザラです(-_-;)
ビジネスモデル的にも1日の売上の上限はほぼ決まっているので、得られる利益も限界があります。
なので飲食業では「多店舗展開」をする人が多いのです。

「店舗数を増やしたために、最終的には1号店も閉店することになった」という話は珍しくありません。
特に昨今の飲食業界は、ビジネス的に不利な状況が続いているので、現段階で多店舗展開を行うのは「賢い選択ではない」と個人的には感じています。
まとめ
ということで今回は「自宅飲食店の開業でやりがちなミス5選」を考えてみました。
やはり自宅で開業するとなると、テナント店舗で開業するよりも「圧倒的に緊張感は少ない」ですよね。
まあ自分もそうだったので、気持ちはよくわかります(^o^;)
ただ、どんなに小さく始めても「事業」である以上、開業準備を怠ってはいけません。
「なんとかなるっしょ♪」の精神では、経営レベル「高難易度」の飲食業では通用しません。
恐らく数年以内に行き詰まって、「こんなはずでは…(-_-;)」と後悔する可能性が高いです。
もし過去の自分のように本業でサラリーマンをやりながら、週末のみ自宅飲食店を経営する場合は
「経営に慣れるまでの猶予期間」
が取れるので、この間に机上と実施で経営を深く勉強していきましょう。(もちろん開業前の勉強も必須)
開業前にやるべき事は
「【開業12年で実感】飲食店経営で役に立つおすすめスキル5選!」
という記事でも書いていますので、よかったらお読みください。
今回の記事が、今後自宅飲食店の開業を考えている方のお役に立てば幸いです。
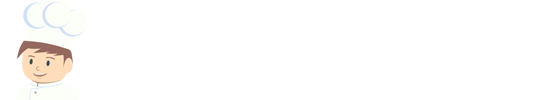


どうもヨッシー店長です。