
2025年4月現在、お米の価格が一向に落ち着かないですね…(-_-;)
子育て家庭も大変だと思いますが、うちの飲食店もかなりダメージを受けています。
去年末に「2025年3月には落ち着くはず」と言われていたので、「利益を減らして耐えてきました」が、半年以上の原価2倍は流石にカバーできなくなってきました。
近々値上げを考えていますが、値上げもそう簡単にはできないところが痛いところです…。(米の価格が2倍になったからといって、店のご飯の販売価格を単純に2倍にするのは難しい)
うちの場合はタイ料理なので『ジャスミンライス』を外して『国産の業務米』にすることも難しいですしね…。
とりあえず現在は「米麺を使用するメニュー」を増やし、メニューで原価分散をしています。
日本人にとって米は「安定安価のインフラ」なはずなんですけどね。。
早く価格が落ち着くことを願います。
ということで今回は、「米の仕入れ価格が高すぎる時の改善策」を考えてみたいと思います。

①仕入れ先の見直し・比較
まずは「仕入れ先の見直し・比較」をしてみましょう。
現在の仕入れ業者に固執せず、他社と比較検討することが大切です。
例えば、地元の農協(JA)や個人農家、または卸売業者に直接交渉すれば、中間マージンを省いて安く仕入れられることがあります。
また、インターネット上にも卸価格で提供している業者が多く、価格競争が進んでいるため、毎年見直す習慣を持つと大きな差になります。
- 複数の業者から見積もりを取り直す。
- 地元の農家や農協(JA)に直接交渉することで中間マージンを削減。
- コメ卸専門業者(例:ミツハシライス、神明、トーヨーライスなど)もチェック。
- 「飲食店向け業務用米」や「規格外米(小粒・割れ米など)」も検討。
②お米の種類・ブレンドの工夫
次に「お米の種類・ブレンドの工夫」をしてみましょう。
単一ブランド米にこだわると高額になりがちです。
業務用として流通している「ブレンド米」は、味とコストのバランスが取れており、一般の飲食店ではよく使われています。
例えば、「コシヒカリブレンド」「あきたこまち+業務用ブレンド米」などは、品質も安定しており、炊き方を工夫すれば味の差もほとんど気になりません。

- ブランド米から、価格が安定している業務用ブレンド米に変更する。
- 例:コシヒカリ100% → コシヒカリブレンドや「あきたこまち+業務用米」など。
③一括購入 or 共同購入
お米はまとめて仕入れると、1kgあたりの単価が安くなる傾向があります。
倉庫スペースや消費ペースに余裕があれば、一度に30kg~60kgの単位で発注するのがおすすめです。
また、近隣の飲食店と協力して「共同購入」を行えば、配送コストや卸価格がさらに安くなる場合があります。
- 大量購入で割引がある業者が多いため、まとめ買いができるならお得。
- 周囲の飲食店と連携して共同購入するのも有効(物流コストも削減)。
④保管・炊飯の工夫でロスを減らす
せっかく仕入れたお米も、炊飯や保存方法が悪いとロスが出ます。
例えば「保温しすぎて味が落ちる」「炊きすぎて捨ててしまう」などのロスは、年間で見ると大きな損失です。
真空パック保存、炊飯量の最適化、温度管理の徹底などでロスを減らすと、仕入れ価格以上にコスト改善が期待できます。
- お米の品質を落とさずに炊飯・保存することで、無駄を削減。
- 例:真空パック保存、保温時間の短縮、保温器の見直し。
- ロス削減により、実質的なコスト削減につながります。
⑤お米の使用量を見直すメニュー構成
ご飯のボリュームをそのままにするとコストがかさみます。副菜やスープを工夫して、ご飯の量を少しずつ減らす工夫をしましょう。
たとえば、丼物やチャーハン、雑炊などは、具材のボリュームでご飯の量を調整しやすく、満足度も下がりにくいです。
- ご飯の量が少なくても満足度が高いメニュー(例:丼物、具沢山おにぎり、雑炊)を強化。
- 副菜やスープで満足感を補い、ご飯の量を自然に減らす工夫。
⑥インターネット業者や農家直販サイトを活用
最近では、農家から直接仕入れられるオンラインサービスが増えており、中間業者を通さない分、価格も安定しています。
例えば、「ポケットマルシェ」や「食べチョク」といったサイトでは、契約栽培や定期購入もでき、品質と価格のバランスが取りやすいです。
また、「楽天市場ビジネス」「Amazonビジネス」などの業務向け通販も便利で、定期購入や法人割引が使えることがあります。
- 楽天市場、Amazonビジネス、ポケットマルシェなどもチェック。
- 定期購入契約を結ぶと割引されるケースもあります。
まとめ
まずは上記のような施策を行ってみて、それでも仕入れ価格が下がらない場合は「値上げ」を検討した方がよいと思います。
インフレ状況になっている以上、ある程度の値上げは仕方ないと思いますし、それまで「お客さんとの信頼関係」が出来ていれば、値上げしたとしても理解してくれる人は多いと思います。
実際、うちの店もこの2年程は「数ヶ月に一度の値上げ」を行っていますが、「お客様が離れた」という印象はほとんどありません。

2年前にウクライナ・ロシア戦争の影響で「小麦粉価格が高騰」し、パンやパスタの価格が上がりました。
そんな中、常に安定した価格の「お米」に注目が集まりました。(主食だから基本的には安価)
それにより「おにぎり専門店」も爆発的に増えました。
…が、まさかそのお米が「2倍の価格になる」なんて誰も考えなかったことですよね。。
正直、インフレで全体的に仕入れ価格の底上げが行われて、かつ輸入食材は円安で価格高騰、そこにインフラとも呼べる米の価格が高騰…と、飲食店にとっては「暗黒時代」が到来しています。
恐らく2025年も多くの飲食店が廃業していくことでしょう…。
現在は「米」が価格高騰していますが、今後は「どの食材もいきなり高騰」の可能性がでてきました。
例えば、安価だと思われている「もやし」「納豆」「豆腐」などもいきなり高騰する可能性だってあります。(米価格が上がった実績から考えると)
そう考えると、取り扱っている食材が高騰しても、対応できる「プランA・プランB・プランC」といった対応準備をしておくのは大事だといえるでしょう。
ちなみに自分は「飲食業界が暗黒時代に入った」と感じて、現在はプランBのビジネスプランを進めています。
今回の記事が飲食店経営者の方に少しでもお役に立てば幸いです。
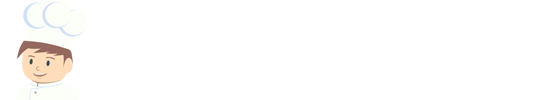


どうもヨッシー店長です。