
これまで(2019年以前)、「飲食業で利益を増やしていこう」と考えた場合、
- まず1号店を成功させる。(収益安定化)
- 1号店をベースに2号店、3号店…と、多店舗展開をしていく。
という方法が、いわば“王道”でした。
しかしながら、昨今の飲食業界は人手不足もあり、多店舗展開の難易度は年々上がっています。

また求人広告費などもバカになりません。
そして、2020年のコロナ禍が訪れ、それまで利益を増やす王道だと思われていた多店舗展開が
「利益を増やすどころか、マイナスになる方法」
に変わってしまいました。(一部店舗を除く)
2020年の途中、国から「家賃支援給付金」や「雇用調整助成金」も出ましたが、多店舗展開を行っている大手企業などは、支援金程度では全てを賄うことはできていない状況です。(実際、店舗の大量閉店や雇止めが発生している)
自分はコロナ禍以前から、
「飲食業の多店舗展開は、全ての店舗で人(従業員)が絡んでくるので、経営リスクは高いだろうな…」
と感じていました。

特に昨今の人手不足や人件費高騰などを考えると余計に…。
また個人的な見解では、1号店を成功させ、オーナーとしてしっかり目が届くのは
「せいぜい3号店くらいまででは?」
と感じています。
これ以上の店舗数になると、どこかで見落としが起き、それをきっかけに「全滅(倒産)」する恐れもあると思っています。

コロナ禍以降、飲食業で多店舗展開を進めることは、ある種“大きなリスク”となってしまいました…。
そんな中、数年前から
「新しいスタイルの多店舗展開方法」
が現れはじめました。
それは…
「ゴーストレストランを利用した多店舗展開方法」
です。
ゴーストレストランの詳細はこちらのページ↓で書いています。
「ゴーストレストランのメリット・デメリットを、飲食店経営者目線で考えてみた」
この「ゴーストレストランを利用した多店舗展開方法」は、
多店舗展開の大きなリスクを「最小限に抑えることが可能」
になります!
なぜ可能かというと…(※後半に続く)
ということで今回は「ゴーストレストランを利用した多店舗展開が超低リスクな理由と、そのメリット・デメリット」を、個人飲食店のオーナー目線で紹介したいと思います。
今後、多店舗展開をお考えの飲食店オーナーさんの参考になれば幸いです。
リアル店舗で多店舗展開を行う場合のデメリット

まず、リアル店舗(路面店)で多店舗展開を行う場合の「デメリット」を箇条書きしておきます。
- 新規の開業費が必要(テナント出店の場合は内装工事費、保証費、広告費などが新規で必要)
- 必要経費の増加(店舗維持費、人件費、各種税金などが増加する)
- 経営管理が複雑化(経費管理、仕入れ管理、スタッフ管理などが単体経営時に比べ複雑化する)
- 間接コストが増加(単体経営時にはいなかった事務員、エリアマネージャーなどの人件費、セントラルキッチンの設置費、商品の配送費などが出てくる)
- サービスクオリティの低下(同店舗間でも一律の同サービスを提供するのは難しい)
- 人材確保が難しい(人手不足の飲食業界で“辞めないスタッフ”を維持するのは難しい)
- 繁盛店の再現性が難しい(1号店が繁盛したからといって、2号店以降が同じような繁盛店になる保証はない)
- “全滅”する恐れがある(1号店のみならやっていけたのに、多店舗展開をしてしまったがために、全てを失う可能性もある)
- 初期投資回収までに時間を要する(大手企業の場合、3~5年以内で回収目標を立てるのが一般的)
- 多店舗展開の成功は正直「賭」(1号店と異なる地域に出店する場合、2号店以降は”地の利”がないため、失敗する可能性も高い)
ざっとですが、上記のような単体経営時にはなかったデメリットが出てきます。
大きく分けると、「資金」と「経営管理」の問題が出てきます。
「経営管理」は個人オーナーであれば、3店舗目くらいまではなんとか管理ができると思います。
時間と共に“経営管理の経験値”も溜まっていくことでしょう。
問題は「資金」の方。
1号店目で余剰資金があればまだいいのですが、多くの経営者はここで公庫や銀行から”融資”を受けることになると思います。
融資を受けるには、1号店目の返済実績なども見られます。
そのため、事前に融資を受ける予定の金融機関で口座を作り、積み立てなどを行い、”信用”を得ていくことが必要になってきます。
信用を得るまでには時間がかかるため、「思い立ったらすぐに多店舗展開!」ということはなかなかできません…。
しかしながら、「ゴーストレストランを利用した多店舗展開方法」を利用すれば、上記の「資金」と「経営管理」の問題を“限りなく小さくする”ことができます!
「経営管理」に関してはそこまで小さくならないかもしれませんが、
「資金」の方は1/100、いや、1/1000にまで抑えることが可能
になることでしょう。
その理由は…↓
ゴーストレストランは「小資本」での多店舗展開が可能!

ゴーストレストランの場合、小資本での多店舗展開が可能といえます。
具体的には、
- 開業資金がほぼ0円
- 新たにかかる経費(特に人件費)もほぼ0円
- 店舗ごとの立地調査費、光熱費(基本料金含む)、研修費などがいらない
開業資金がほぼ0円
既に店舗(1号店)があるわけですから、新たな開業資金(保証金、礼金、内装工事費など)は必要ありません。
※後述しますが、通常新たなリアル店舗を出店する場合、数百万~数千万円の資金が必要になってきます。
その代わり、ネット環境設備(受注用タブレット端末、Wi-Fi環境など)は必須なので多少支出があります。(せいぜい20万円以内)
新たにかかる経費(特に人件費)もほぼ0円
リアル店舗で多店舗展開をする場合、出店数分の「新たな店舗家賃、人件費」などが必要となりますが、ゴーストレストランで多店舗展開をする場合は、これらが“ほぼ0円”で済みます。
- 店舗家賃→既存店(1号店)で既に支払っている!
- 人件費→既存店(1号店)のスタッフで対応可能!
特に「新たな人件費がほぼ0円」というのは、
飲食業界に革命を起こす程の“とてつもなく大きなメリット”
です。
※ただし、スタッフのキャパオーバーになった場合は、新たなスタッフ採用も必要。
店舗ごとの立地調査費、光熱費(基本料金含む)、研修費などがいらない
リアル店舗で多店舗展開をする場合、既存店(1号店)と異なる地域に出店する時は「その地域の立地調査」が必要になってきます。
これにはもちろん費用がかかります。(一般的に10万円以上はかかってくる)
しかしゴーストレストランで多店舗展開をする場合は、既存店(1号店)と同立地になるため、新たな立地調査が必要ありません。(立地調査費削減)
立地調査費がかからない上に、「その立地の客層や雰囲気を既に理解している」のは大きなメリットになります。(地の利がある)
また、既存店なので、新たな光熱費(基本料金含む)やスタッフの研修費などもかかりません。
これらは開業費に比べれば少額ですが、積み重なれば大きな支出となります。
ただし、ゴーストレストランは基本的にデリバリーとなるため、備品代(容器、カトラリー、袋など)は別途必要になってきます。
※この経費は意外とバカになりません。
ゴーストレストランは「低リスク」での多店舗展開が可能!

ゴーストレストランの場合、低リスクでの多店舗展開が可能といえます。
具体的には、
- ほぼ無限に多店舗展開が可能
- 開店閉店を繰り返し、地域性にあった業種の模索が可能
ほぼ無限に多店舗展開が可能
ゴーストレストランの場合、ネット上に店舗を出店するわけですから、事実上「ほぼ無限に多店舗展開が可能」といえます。(※プラットフォームによっては制限あり)
もちろん店舗の製造能力、既存スタッフのキャパシティなどに関わってくるので、実際には無限ではないですが、例えば既存店(1号店)内で「異なる業種の専門店を10店舗展開する」ということも可能になります。

「異なる業種の専門店を2~3店舗」というのが無理なく運営できる範囲だそうです。
自分が一人でやるなら、多分「カフェガパオのデリバリー版」として1店舗のみ運営すると思います。2店舗以上だと管理が大変だと思うので。。
開店閉店を繰り返し、地域性にあった業種の模索が可能
ゴーストレストランは出店費用がほぼかからないこともあり、開廃業が容易にできます。
そのため、地域のニーズに合う業種を見つけ出すまで、開店閉店を繰り返すことが可能です。
例えば…
- 一度に「ビーガンメニュー専門店」「カツ丼専門店」「ドライカレー専門店」「オードブル専門店」を開業。
- 半年後「ビーガンメニュー専門店」「オードブル専門店」が売上的に良かった。
- その後「カツ丼専門店」「ドライカレー専門店」は閉店。
- 1年後「ビーガンメニュー専門店」が圧倒的に売上が良いことがわかる。
- 「オードブル専門店」は閉店。
- 「ビーガンメニュー専門店」を維持しつつ、今度はそのジャンルに近い「ベジフード専門店」「朝どれ野菜スムージー専門店」「大豆ミート料理専門店」を開業させる。
こんなことが可能になります。
大手企業のリアル店舗は、立地調査をした上で、その地域に合った業種業態で開業しますが、それでも“絶対当たる”という保証はありません。
見誤ると、出店費用(数百万以上)が泡と消えてしまう可能性もあります。(もしくは回収期間が長期になる)
ゴーストレストランの場合は、この
「当たるかどうかの検証が“ノーリスク”」
で出来てしまうところが凄いところです。
個人飲食店でも「小資本・低リスク」での多店舗展開が可能!

前述したような「小資本・低リスクでの多店舗展開」が、個人飲食店でも可能です。
そして個人飲食店の場合、完全なゴーストレストラン(お客さんが来店しない店舗)には無い、ある「2つのメリット」が加わります。
それは、
- リアル店舗からプロモーションが出来る
- ネット上でも信頼を得やすい
という点。
リアル店舗からプロモーションが出来る
個人飲食店の場合、店内のポップやホームページ等で『デリバリー始めました!』などと、既存客にお知らせ(プロモーション)をすることが可能です。
完全なゴーストレストランはリアル店舗が無いため、これができません。
完全なゴーストレストランに比べ、個人飲食店はこの部分がまずはアドバンテージとなります。
ネット上でも信頼を得やすい
現在デリバリーの分野では、『マクドナルド』や『すき家』など、チェーン店の利用が圧倒的に多い状況です。
なぜチェーン店の利用が圧倒的に多いのか?
それは「既に味を知っているから」です。
デリバリー以前から店の味を知っているので、デリバリーになっても安心して注文できるわけです。
つまり、リアル店舗がある場合「信頼がある(既に味を知っている)ため、デリバリー注文がされやすい」といえます。
完全なゴーストレストランは、ネット上にしか店舗がないため、この部分ではかなり不利です。(味見する場所が無い)
恐らく商品写真やクチコミ等で判断する他ありません。(初回注文の場合)
なので、既に人気のある個人飲食店であれば、多くの人がその店の味を知っているので、デリバリー分野に参入したてでも「それなりにデリバリー注文がされやすい」といえるでしょう。
リアル店舗とゴーストレストランの開業費・経費比較

ここで一旦、リアル店舗とゴーストレストランの「開業費と経費」を比較してみたいと思います。
※どちらも郊外エリアの個人飲食店とする。
※多店舗展開する店舗数は、1店舗のみとする。
※ゴーストレストランは既にリアル店舗(1号店)があるとする。
※ゴーストレストランは従業員は増やさないものとする。
※ゴーストレストランは『UberEats』などの初期費用が掛からないデリバリープラットフォームを利用するとする。
※金額はあくまでも参考価格。
※経費は1ヶ月分のものとする。
開業費比較
| リアル店舗を1店舗増やす | ゴーストレストランを1店舗増やす | |
| 保証金 | 300万円 | 0万円 |
| 礼金 | 30万円 | 0万円 |
| 仲介手数料 | 30万円 | 0万円 |
| 前家賃 | 30万円 | 0万円 |
| 厨房機器費 | 100万円 | 0万円 |
| 看板施工費 | 20万円 | 0万円 |
| 内装・設計費 | 150万円 | 0万円 |
| 求人広告費 | 10万円 | 0万円 |
| 販売促進費 | 40万円 | 10万円 |
| 備品費 | 30万円 | 20万円 |
| 合計 | 740万円 | 30万円 |
新たにリアル店舗を1店舗増やす場合の合計金額は「740万円」なのに対し、
ゴーストレストランで1店舗を増やす場合の合計金額は「30万円」となりました。
※完全無店舗型のゴーストレストランだともう少し費用はかかりますが、それでも数十万円あれば開業できることでしょう。
備品費20万円の内訳は、受注用タブレットやネット環境設備、容器やカトラリー類など。
受注用タブレットやネット環境設備が既にある場合は、半額以下(10万円以下)で開業することができるでしょう。
あくまで参考金額でしかありませんが、開業費用で既に「710万円もの差」が出ています!
もしリアル店舗であれば回収するまでに数年かかる金額ですが、ゴーストレストランなら早ければ半年以内に回収できる金額だといえるでしょう。
ゴーストレストランで多店舗展開をする大きなメリットが、まずこの「開業費の低さ」です。
経費比較
| リアル店舗を1店舗増やす | ゴーストレストランを1店舗増やす | |
| 店舗家賃 | 10% | 0% |
| 人件費 | 40% | 0% |
| 食材原価 | 30% | 30% |
| 光熱費 | 5% | 3% |
| 雑費 | 5% | 7% |
| プラットフォーム利用料 | 0% | 35% |
| 利益 | 10% | 25% |
経費の割合は大雑把な数字ではありますが、リアル店舗の場合は1号店とそれ程変わらない経費がかかります。
利益も10%出れば良い方だといえます。
ゴーストレストランで多店舗展開をする場合は、店舗家賃と人件費が「実質0%」になります!(今回の設定条件では)
これはかなり大きいです!
この時点で経費が「50%削減」できる計算になります。
その他の内訳は…
食材原価はほぼ変わらず、光熱費は基本料が無い分減ります。
雑費は容器代などが新たにかかるため少し増加。
そしてリアル店舗には無い「プラットフォーム利用料」が新たにかかります。(ゴーストレストランではこれが一番大きい経費)
正直プラットフォーム利用料は高いですが、それでも最終的には「25%の利益」が出る計算になります。
詳しくはこちらの記事↓で書いています。
「ゴーストレストランのメリット・デメリットを、飲食店経営者目線で考えてみた」
ということで「開業費と経費」を比較してみましたが、ここまでを総評してみると…
ゴーストレストランで多店舗展開をする場合は、
- 開業費は、リアル店舗の1/20以下
- 経費は、店舗家賃と人件費が無くなる分、プラットフォーム利用料が増えるが、利益が25%も出る
となりました。
既にリアル店舗(1号店)を経営している人には、ゴーストレストラン(デリバリー事業)に参入するのは「大きなメリットがある」といえそうです。
ゴーストレストランで多店舗展開する場合のデメリット

資金面で大きなメリットがある「ゴーストレストランでの多店舗展開」ですが、デメリットも存在します。(この世の全ての事には良い面と悪い面が必ず存在する)
デメリット①「管理が大変」
リアル店舗を運営しながらゴーストレストランも運営する場合、リアルタイムの顧客管理数(注文数)は確実に増えます。
ピークタイムではオーダーが重なる場合も多々あるので、効率良く回していかないと、顧客満足度が下がる可能性があります。
※『注文した料理が出てくるのが遅い!』とクレームになる場合も。
そのため、現行の運営時にある程度余裕がないと、リアル店舗とゴーストレストラン (デリバリー)を同時に運営するのは難しくなるでしょう。
各プラットフォームでは、オーダーの「緊急停止設定」があるので、リアル店舗が忙しくなった時はそちらをオンにして対応することになります。
緊急停止設定はありますが、ゴーストレストラン (デリバリー)を出店している以上、「ずっと停止中」だと店舗の印象は悪くなってしまいます。
やはり運営するには「ある程度余裕がある状態が望ましい」といえます。
デメリット②「プロモーションが大変」
「ゴーストレストランのメリット・デメリットを、飲食店経営者目線で考えてみた」でも書いていますが、ゴーストレストランはプロモーション(自店を知ってもらう努力)が大変です。
1店舗でも大変なのに、これを多店舗でやらなくてはいけません。
また、リアル店舗とは違う「ゴーストレストランならではのマーケティング(WEBマーケティング)」が必要になってきます。
このマーケティングを勉強するのには、それなりの時間を要すると思います。
※自分はこちら↓でお勉強。
ただし、前述したように既存店(1号店)がある場合は「リアル店舗からプロモーションが出来る」ので、その部分は有利になります。

デメリット③「プラットフォームの対象エリア内でしか店舗を増やせない」
ゴーストレストランは「プラットフォーム(UberEats・出前館など)ありきのビジネスモデル」のため、それらが対応しているエリアにしか出店できません。
もし既存店(1号店)がある地元エリアで「ゴーストレストランの多店舗展開をしたい!」と思っても、地元が対応エリアになっていなければ、その場所では多店舗展開ができません。

これに関しては、プラットフォームが対応エリアになることを待つしかありません。
デメリット④「そもそも市場規模が小さい」
ゴーストレストラン(デリバリー)は、リアル店舗に比べると市場規模は「まだまだ小さい」です。
例えば、地元エリアにリアル店舗が100店あったとして、その中でデリバリー対応もしている店舗は、大手チェーンを除けば数店舗あるかないかといった地域も多いことでしょう。(都内と地方では差がありますが)
利用ユーザーも以前よりは増えていますが、それでもイートインやテイクアウトの方が一般的といえるでしょう。
つまり、ゴーストレストランで多店舗展開を始めたとしても、そもそもの利用者が少ないので、すぐに注文されるかどうかはわかりません…。
ただし、昨今のコロナ禍で「デリバリー需要」は増えているため、今後ゴーストレストランの利用者数は確実に増えていくでしょう。
そういう意味では、「デリバリー業態はまだまだ伸びしろがある」とも言えます。
ゴーストレストランの今後

「デリバリー」は今後も伸びていく
2019年以前は、飲食店での食事というと「イートイン(店内食事)」「テイクアウト」がメインでした。
2020年以降は、コロナが追い風となり「デリバリー」という選択肢が、一般でも定着していきました。
2021年以降は、プラットフォームの対応エリアが益々増えていることもあり、デリバリーに参入する店舗も今後増えていくと思われます。
コロナが終息した後も、「デリバリー」という選択肢はなかなか消えないでしょう。
※「届けてもらうのって便利♪」と知った人が一定数いるので。
今後は「コロナと関係ない需要」
- 小さい子がいてなかなか外食できないママ
- 足が不自由な高齢者
- 悪天候時に外出を控えている人
などで、「デリバリー」が利用されていくと思われます。
また、新たなウイルスが流行した際、再度「デリバリー」に注目が集まることでしょう。
個人店は「ゴーストレストランで多店舗展開」が主流になる?
今後は「ゴーストレストランで多店舗展開」をしていく企業・店舗も増えることでしょう。
※実際、ゴーストレストランで多店舗展開を進めている大手企業もあります。
特に個人飲食店は「ゴーストレストランによる多店舗展開」との相性が良いように思います。
なぜなら小資本・低リスクで多店舗展開が始められるからです。
『小資本・低リスクで多店舗展開できるならやってみたい!』というオーナーさんも多いと思います。

個人的には、小資本・低リスクで多店舗展開ができるゴーストレストランという業態は、今後「個人飲食店で主流になっていくのでは?」と感じています。
ゴーストレストランで多店舗展開 まとめ

ということで今回は「ゴーストレストランを利用した多店舗展開が超低リスクな理由と、そのメリット・デメリット」を、個人飲食店のオーナー目線で紹介してみました。
以下、今回のまとめです。
- リアル店舗で多店舗展開を行う場合のデメリットは、主に「資金」と「経営管理」
- ゴーストレストランは「小資本」での多店舗展開が可能!
→開業資金がほぼ0円
→新たにかかる経費(特に人件費)もほぼ0円
→店舗ごとの立地調査費、光熱費(基本料金含む)、研修費などがいらない - ゴーストレストランは「低リスク」での多店舗展開が可能!
→ほぼ無限に多店舗展開が可能
→開店閉店を繰り返し、地域性にあった業種の模索が可能→当たるかどうかの検証が“ノーリスク” - 個人飲食店でも「小資本・低リスク」での多店舗展開が可能!
さらに
→リアル店舗からプロモーションが出来る
→ネット上でも信頼を得やすい
というメリットもある - 「リアル店舗で多店舗展開」と「ゴーストレストランで多店舗展開」を比較した場合、
→開業費では、ゴーストレストランで多店舗展開した方が「710万円も安くなる」(※金額は仮定)
→経費では、ゴーストレストランで多店舗展開した方が「利益が25%になる」 - ゴーストレストランで多店舗展開する場合のデメリット
→管理が大変になり、顧客満足度が下がる可能性がある
→ゴーストレストランならではのマーケティングが必要になるため、プロモーションは大変になる
→プラットフォームの対象エリア内でしか店舗を増やせない
→そもそも市場規模が小さい、ただし「デリバリー業態はまだまだ伸びしろがある」とも言える - ゴーストレストランの今後
→「デリバリー」は今後も伸びていく、今後はコロナと関係ない需要でも活躍
→小資本・低リスクで多店舗展開ができるゴーストレストランは、今後個人飲食店で主流になっていくのでは?
今回の記事が「多店舗展開を考えているオーナーさん」のお役に立てば幸いです。
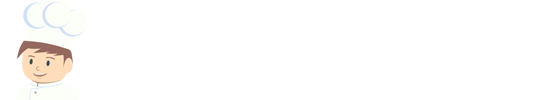


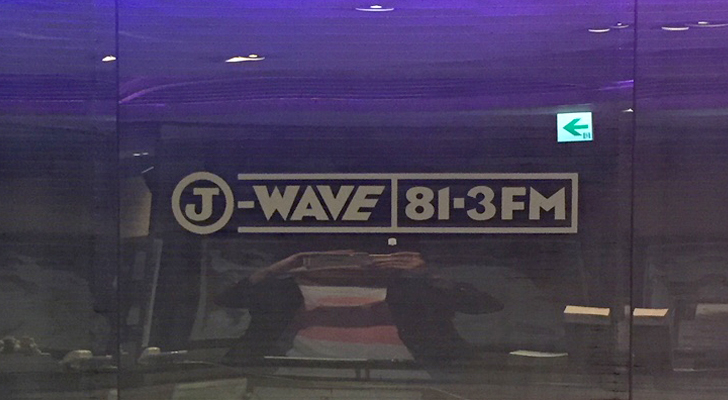
どうもヨッシー店長です。